小学校入学を控えた、年長ママさんたちは、「小学生になって、勉強に取り組めるか心配」、「お友達や学校という環境になじめるのか不安」という方も多いと思います。
そこで今回は、小学校入学前に、幼稚園や保育園のうちからやっておくといいことについてまとめました。
「あれもやらなきゃ」「これもやらなきゃ」と気負うことはありませんが、少しずつ入学に向けて準備をしておくと、親子とも小学校生活での不安を少しでも軽減できると思います。
よかったら参考にしでください。
小学校ってどんなところ?何をするの?ということを知る
小学校に入学するにあたっては、「そもそもなんで小学校に通うの?」「小学校ってどんなところ?」という疑問を抱くお子さんもいらっしゃると思います。
幼稚園や保育園との違いや、小学校でどんな活動をするのか、事前にイメージがあると、不安も和らぎます。
小学校の環境に合わせた生活習慣の準備
早寝早起きの習慣をつける
幼稚園や保育園は、施設によっても異なりますが、登園時間が9時ころまでのことが多いですが、小学校は、それよりも早く登校することが多くなります。
持ち物準備や片付けを自分で
持ち物の準備や片付けを、徐々に自分で行えるようにしていきます。
トイレのタイミングと使い方
授業中はなるべくトイレに行かず、休憩時間に行っておくのが基本であると伝えます。
しかし、どうしてもトイレに行きたい場合ももちろんあります。そういった場合は、我慢せず先生に言ってから行くよう伝えておきます。
お昼寝が多い子は?睡眠の質を高める
幼稚園や保育園の中には、お昼寝の時間があったり、日中まだまだ眠気のある子もいるかと思います。
なるべく学校では昼寝をしないよう、上述した早寝早起きの習慣をつけておきます。
それでもなお日中うとうとしているなあ、という場合は、睡眠の質をチェックします。
寝室の厚さや寒さで夜中に起きてしまったり、夜中トイレに起きていないかなどをチェックします。
学習の基礎準備
鉛筆の持ち方、消しゴムの使い方
学習の基本として、鉛筆を正しく持つことや、消しゴムで文字を消す練習を、ドリルやお絵かきなどをしながらやっておきます。
鉛筆の正しい持ち方の習慣化におすすめなのは、KUMONの三角鉛筆。鉛筆が三角になっているため、自然ときれいな持ち方になり、太めで子どもでも握りやすくなっています。
ひらがなの読み書き
ひらがなの読み書きは、入学後でもできるので、全部を完璧にできていないくても大丈夫です。
ただ、持ち物やロッカーの場所を把握するうえでも、自分の名前の読みができていると安心です。
こちらに、ひらがなを覚えるための工夫についてまとめた記事もありますので、よかったらご覧ください。

算数遊び
1~10の数がいえたり、その数がどのくらいの量なのかという基本的な概念を、遊びを通じて知っておくのがおすすめです。
おやつの数を数えたり、兄弟で分けたりするだけでも、基本的な計算ができます。
絵本はなるべく毎日触れる
絵本は、語彙力を高めたり、想像力を広げてくれます。また、読み聞かせをすることで、話を聞く集中力や理解力を身に着けることにもつながります。
心や感情の成長にもつながりますし、内容によっては道徳観や社会性などを学ぶこともできます。
椅子に座って作業する
小学校では、学習する時間が多くなります。
そのため、きちんと椅子に座って話を聞いたり、作業することができることが大切になります。
お子さんの興味や関心のあることを一緒に楽しむ時間を大切にする
子どもと一緒に過ごす時間も、小学生になると少しずつ短くなっていくことも多いと思います。
保護者の就労や、子どもの交友関係の拡大など、親が子どもに多くの時間をかけてあげられる時間も減っていきます。
小学生では、空いている平日に自由に休みを取ることは難しくなりますし、旅費もかかるようになってきます。
そのため、平日でも比較的休みをとりやすい就学前は、お子さんの好きなことや興味のある場所におでかけすると、今しかできない思い出づくりになります。
通学路や交通安全の確認
通学路の確認は、毎日登下校する子どもが安心できるよう、少しずつ練習しておくと安心です。
実際に一緒に歩いてみて、危険な個所をチェックします。「ここは必ず止まって左右を確認しよう」など、具体的に声をかけて、注意を促します。
横断歩道を渡るときのルールも一緒に確認したり、不審者への対応なども伝えておきます。
また、朝と午後など時間帯を変えて歩いてみると、交通量や人通り、夏場は気温、冬場は日の入りなど、注意点も変わってくることがあります。親の目で実際に行って確かめておくことをおすすめします。
小学校生活のための準備
小学校生活が始まると、園での生活とは違い、自分のことは自分で行うようにする、ということが増えていきます。
例えば、
- ランドセルの開け閉めの仕方や、背負うことになれておく
- 給食のエプロンを着られるようにする
- 体操着をたたんでしまうことができる
- ハンカチ・ティッシュは毎日ポケットにいれて、学校から帰ったらポケットから出す
- カバンの準備の習慣をつける
- 時計を見て準備をする(完璧でなくてもいいので、時計を見る習慣をつける)
就学前の説明会などで、必要な持ち物について確認をします。
また、学童保育を検討している場合は、入学前から募集が始めることもあるため、自治体のホームページで情報を確認しておきましょう。
困ったときにSOSが言える 何を困っているかが伝えられるようにする
授業がスタートすると、集団での行動場面が増え、自由に行動することができなくなります。
例えば、急にトイレに行きたくなったり、体調が悪くなってきてしまうこともあります。
なるべくトイレは休憩時間に行けるようにしつつ、もしも急に行きたくなったときには、我慢せず行かせてもらえるよう、自分で申告する必要があると伝えます。同様に、体調が悪いときは、保健室に行かせてもらうことも大切です。
また、様々な友達や、学年を超えた人間関係、先生との関わりの中で、困ったことやトラブルが起きる場合もあります。
身近な先生に相談したり、親子で話ができるように配慮することも大切です。
まとめ
今回は、年長のうちからできる、小学校入学に向けてやっておくといいことについてまとめました。
勉強を進めておかないと、と不安になることもありますが、入学後にしっかりと勉強を教えてもらえるので、無理に勉強を進めなくても大丈夫です。
生活面や心の準備、学習の基礎を少しずつ行い、自分でできることを増やしながら、「学校って楽しそうだな」と少しでも思えたら、準備はOKだと思います。
ぜひできそうな項目をやってみてください。

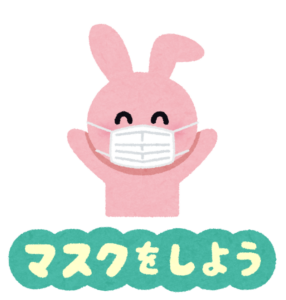



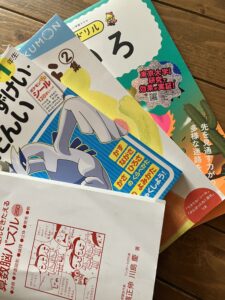
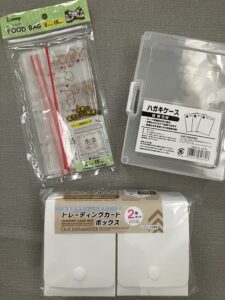


コメント